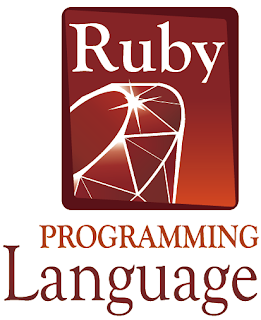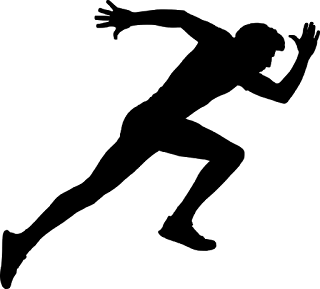ruby: Ruby on Rails逆引きコマンド集
開発環境操作 rake で利用するタスクを生成したい 現在のenvironmentを確認する テスト用サーバを外部公開したい アプリケーションのタイムゾーンを設定する アプリケーションのロケールを日本語にしたい / 日本語を利用する方法 UbuntuでバックエンドとしてPostgresを使うようにしたい モデル操作関連 ActiveRecord(データ)を検索したい ActiveRecord(データ)を範囲検索したい / 絞り込みたい ActiveRecordの並び替えをしたい CSVからデータベースにRecordを格納したい development, production, test などの切り替え View関連 CSSファイルを外部から読み出す設定の方法 Paginationしたい / 数が多いので分割して表示したい 番外編: Kaminariを使うと変なスペースが導入される DateTime を任意の文字列形式で表示したい 現在のroutes を一覧表示 お問い合わせフォームを作成したい 確認バージョン: Rails: 7.0.3.1 Ruby: ruby 3.1.2p20 (2022-04-12 revision 4491bb740a) 開発環境操作 rake で利用するタスクを生成したい bin/rails g task < namespace > < task_name > 例えば bin/rails g task test_job test_task ./lib/tasks の下に test_job.rake が作成されている。 それ以降は Ruby on Rails での rake タスク作成 の記事参照。 現在のenvironmentを確認する 以下のコマンドによって確認可能。 rails r "puts Rails.env" テスト用サーバを外部公開したい リモートで開発している際などで、 bin/rails s で puma を利用して稼働させたデバッグレベルのサーバを外から確認する必要があるとき。バインドするアドレスを変更する。 bin/rails s -b 0.0.0.0 ポ...